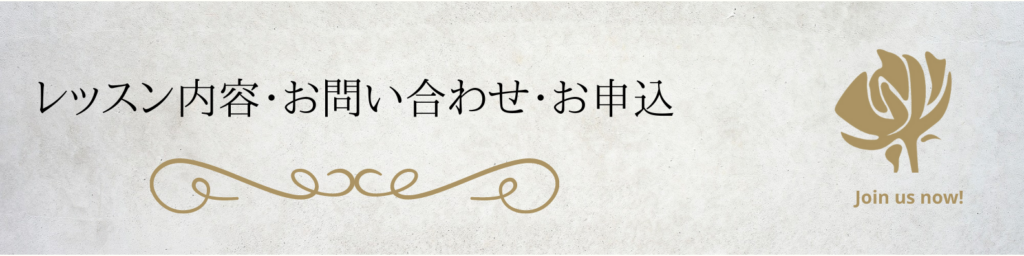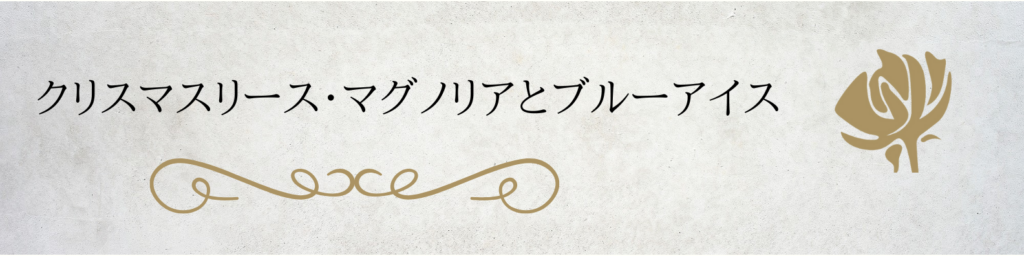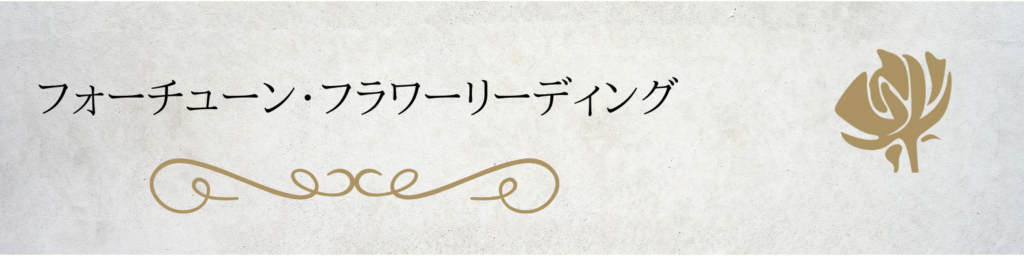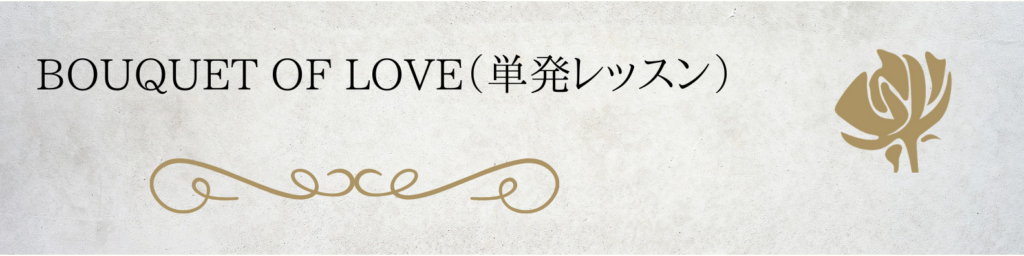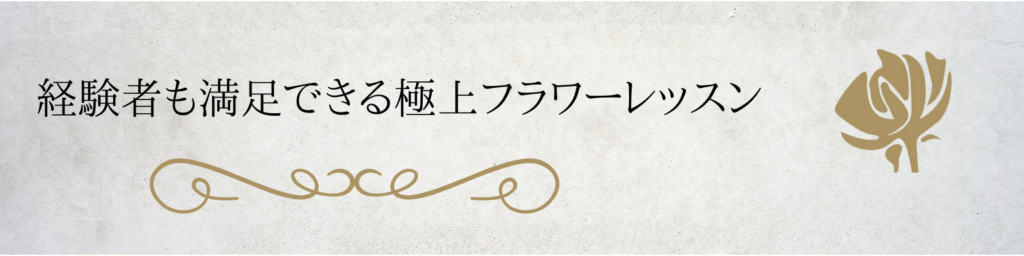1,世田谷市場へ – 裏日の訪問記とその魅力
表日と裏日の違いや、裏日の静けさを楽しんだ市場訪問記。
2,資材屋さんの利用経験と市場の利便性
世田谷市場の資材屋さんの便利さと、過去のエピソードを交えた利便性の紹介。
3,コンパクトで効率的な市場の構造
円形構造やショートカットの利便性、エアコン完備の快適な環境について。
4,年末に向けた市場の準備 – 松市と千両市
年末の特別なセリや市場の年末年始スケジュールについて。
5,世田谷市場の基本情報と特徴
世田谷市場の歴史や花き部門、仲卸業者の役割を解説。
6,世田谷市場まつり – 地域をつなぐイベント
市場まつりの内容や模擬セリ、地域活性化の取り組み。
7,今日の市場訪問を振り返って
裏日ならではの静かな市場探訪と、年末準備への意気込み。
1,世田谷市場へ – 裏日の訪問記とその魅力
東京卸売市場の花き部門です。
花きとは
花き(かき)とは
観賞用として栽培される植物を指します。
具体的には、切り花、鉢物、花木類、球根類、花壇用苗もの、
芝類、地被植物類などが該当します。
花きは、冠婚葬祭や贈答用、装飾など、
さまざまな用途で使用されています。
花きの栽培は、適切な土壌、水分、光、温度管理が重要で、
温室での栽培が一般的です。
ビニールハウスなどで栽培されることが多く、
農業知識だけでなく、
需要と供給の関係を見る商売勘も必要とされる農業です。
花きは生鮮食料品などと同じように、
保存が難しく、生産量が自然条件により左右され、
価格が変わりやすいという特性を持っています
・・・・・・・

昨日も訪れた世田谷市場に、
急遽必要なものがあり、
裏日の今日も足を運ぶことになりました。
世田谷市場には「表日」と「裏日」があり、
表日(月・水・金)は切り花のセリが行われるため、
非常に活気があります。
特に12月に入ってから、
満員電車のようです。
みなさん、枝物とか
を担いでいるので
顔にぶつからないように注意が必要です。
一方で、今日は裏日ということもあって、
人の少なさが目立ちます。

市場特有の賑やかな雰囲気が少ない分、
のんびりと市場を探索することができました。
空いている市場内を歩き回りながら、
写真を撮る余裕もありました。
やはり改めて感じるのは、
世田谷市場のコンパクトさと利便性。
大田市場に比べて規模が小さいため、
移動がスムーズで、必要なものに
すぐアクセスできる点がとても助かります。
コンパクトな市場ですが、
必要なものはほとんど揃っており、
資材屋さんも利用しやすく、
花の仕事をする私にとって非常に便利な存在です。

2,資材屋さんの利用経験と市場の利便性
世田谷市場内には資材屋さんが2軒しかありません。
一見すると少ないように思われるかもしれませんが、
必要な資材はしっかり揃っています。
さらに、もし在庫がない場合でも、
取り寄せ対応をしてくれるため、安心して利用できます。
以前のエピソードですが、
横浜のディスプレイミュージアムで、
1年分のレッスン用サンプルの器を選ぶために
長時間をかけて吟味したことがありました。
しかし、いざレッスンの際に仕入れようと思ったら、
「あら、ここにあるじゃない!」と気づきました。
世田谷市場の資材屋さんには日常使いに必要なものが
きちんと揃っており、地元市場の重要性を改めて実感しました。
このように、世田谷市場の資材屋さんは
私たちフラワーコーディネーターにとって
頼りになる存在です。
さらに、資材屋さんとのコミュニケーションを通じて、
新しい情報やおすすめの商品を知ることができるのも魅力の一つです。
3,コンパクトで効率的な市場の構造
世田谷市場の建物は、円形構造が特徴です。
このユニークな設計は、土地を有効活用しており、
どこにいても効率的に動けるようになっています。
特に「インコース」を歩くと、
ショートカットができるので便利です。
市場全体がシンプルで分かりやすい造りになっているため、
初めて訪れる方でも迷うことが少ないでしょう。
また、夏の暑い日には、
建物内にエアコンがしっかり効いているため、
快適に作業ができる環境が整っています。
市場といえば開放的な空間を想像しがちですが、
世田谷市場では屋内施設の快適さが際立っています。
この細やかな配慮も、
多くの業者に支持される理由の一つです。

市場内は大きく3つのエリアに分かれています。
-
南棟:切り花のセリが行われるメインエリア。
-
中央棟:仲卸や資材屋さんが集まるエリア。
-
地下フロア:青果市場が広がっています。

今日は中央棟から円の中心にある階段を降り、
地下の青果市場へ足を運びました。

下に着くと、人が少なくシーンと静まり返っており、
少し不気味に感じるほどでした。
丸い建物特有の構造のせいか、
自分がどこにいるのか一瞬分からなくなる場面もありました(笑)。
でも、ぐるっと回って無事に入り口を見つけることができて一安心です。

4,年末に向けた市場の準備 – 松市と千両市
南棟に戻り、エレベーターで3階へ上がると、
明日の松市に向けた準備が行われていました。
松市とは、お正月用の松を扱う特別なセリで、
年末の風物詩の一つです。
「明日も来る?」と市場の方に声をかけられましたが、
私は行く予定はありません。
松の保管は非常に手間がかかるため、
私は仲卸でギリギリに仕入れることにしています。
ちなみに、今年の千両市は12月18日。
お正月を彩る千両を扱う特別な市場です。
市場全体が少しずつお正月ムードに包まれてきており、
忙しさも一層増していく時期となります。
今年最後のセリは12月28日の「留市」と呼ばれる日。
そして新年最初の「初市」は1月4日ですが、
成人式の時期までは花の種類が少ないです。
年末年始はフラワー業界にとって特別な時期。
世田谷市場での仕入れも
一段と忙しくなることが予想されますが、
この市場が近くにあるおかげで安心して準備を進められます。

5,世田谷市場の基本情報と特徴
ここで、世田谷市場について簡単におさらいしてみましょう。
世田谷市場は1972年に開場した東京都中央卸売市場の一つで、
青果物と花きを専門に取り扱っています。
環状8号線沿いに位置し、
東名高速や首都高速の用賀インターチェンジにも近いため、
アクセスが非常に便利です。
特に花き部門では、切り花専門の
「世田谷花き」と鉢物専門の「東京砧花き園芸市場」の2社が運営しており、
地域の花卉流通を支える重要な役割を果たしています。
市場内では、
オランダ式の競りシステムが導入されており、
効率的で公平な取引が行われています。
また、仲卸業者が6社あり、
生花店やイベント業界など、
さまざまな顧客のニーズに応えています。
市場内で働く人々の熱意と技術力が
高品質な花々を支える要因となっています。

6,世田谷市場まつり – 地域をつなぐイベント
世田谷市場では毎年「世田谷市場まつり」が開催され、
市場の魅力を広く伝える場となっています。
このお祭りでは、青果物や花の即売、
模擬セリ、和太鼓の演奏、食育講座など、
多彩なプログラムが用意されています。
普段は見ることのできない
市場の裏側を知ることができる貴重なイベントです。
特に模擬セリは人気のプログラムで、
市場ならではの臨場感を体験できます。
お子様から大人まで楽しめるこのイベントは、
地域の活性化にも一役買っています。
次回開催の情報は公式ウェブサイトで随時更新されるため、
興味のある方はぜひチェックしてみてください。

7,今日の市場訪問を振り返って
最後に、渡り廊下を渡り中央棟に戻り、
車に乗り込みました。
裏日の市場は静かで少し不気味に感じることもありましたが、
その分、落ち着いて市場の魅力を再発見できました。
世田谷市場のコンパクトさ、利便性、
そして地域に根付いた温かさを改めて実感しました。
この訪問記を通じて、
世田谷市場の魅力を
少しでも感じ取っていただけたら嬉しいです。
市場の活気あふれる表日とはまた違った静けさの中で、
見えてくるものがたくさんありました。
今年も残りわずかですが、
年末年始の準備をしっかり進め、
充実した新年を迎えたいと思います。
 毎回、砧公園の紅葉をちょっとだけ楽しみにしています。
毎回、砧公園の紅葉をちょっとだけ楽しみにしています。
・・・・・・・・・・